前立腺がん
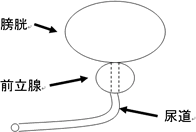 前立腺は図のように尿道の一部を構成しているとともに、男性の精液の一部をつくる臓器です。大きさは10代前半の初年期では10g以下ですが、思春期になると急速に大きくなり、20代になると約20gに達します。 前立腺がんは他のがんに比べ高齢者に多く、アメリカでの男性のがん罹患率では第1位となっています。日本でも食生活の欧米化など生活習慣の変化に伴い増加の一途をたどっています。 早期がんでは自覚症状がないために、以前は骨に転移するなどの進行がんになって初めて見つかる患者さんがほとんどでしたが、血清PSAという血液検査を行うようになってから、早期がんの患者さんがたくさん見つかるようになりました。
前立腺は図のように尿道の一部を構成しているとともに、男性の精液の一部をつくる臓器です。大きさは10代前半の初年期では10g以下ですが、思春期になると急速に大きくなり、20代になると約20gに達します。 前立腺がんは他のがんに比べ高齢者に多く、アメリカでの男性のがん罹患率では第1位となっています。日本でも食生活の欧米化など生活習慣の変化に伴い増加の一途をたどっています。 早期がんでは自覚症状がないために、以前は骨に転移するなどの進行がんになって初めて見つかる患者さんがほとんどでしたが、血清PSAという血液検査を行うようになってから、早期がんの患者さんがたくさん見つかるようになりました。
症状
前立腺がんの初期にはほとんど症状はありません。前立腺肥大症と合併することが多いため、前立腺肥大症と似た症状が現れることがあります。進行すれば排尿困難や血尿を伴ってきたり、また更に進行すれば骨に転移して腰痛などが出現してきたりすることもあります。
診断
診断には、肛門から指を入れて前立腺を触って大きさや硬さを調べたり、血液検査で前立腺腫瘍マーカー(PSA)を調べたりします。これらの検査で前立腺がんが疑われれば、超音波で前立腺を観察しながら、前立腺に針をさして組織の確認(生検)を行い、顕微鏡による診断(病理組織診断)を行います。このときに、がんの悪性度(性質が良いか悪いかのことです)を詳しく調べます。がんが見つかったら、次には進行度(どのくらい広がっているのか)を調べますが、CT、MRIや骨シンチグラフィーという検査で行います。この悪性度と進行度によって、その後の治療方針が違ってきます。
悪性度の診断
我が国の前立腺がん取り扱い規約(泌尿器科・病理)では、分化度を高分化、中分化、低分化、分化度分類不能と分類していますが、いちばん顔つきのよいのが高分化、いちばん顔つきの悪いのが低分化ないし分化分類不能です。最近では、Gleason scoreという方法の方が良く使われるようになっています。このscore は最低が4点、最高が10点で低いほど顔つきが良いです。4以下の場合、リンパ節転移の確率は少ないと考えられています。進行度の分類 広がり具合、すなわち病期を初期から進行期へ向けてA、B、C、Dの 4期に分けています。
病期A
たまたま前立腺肥大症の手術を受けた際に、その前立腺の中に前立腺がんが発見されたものです。さらにA1とA2に分け、A1は片葉内に限局しかつ高分化腺がんであるもの、A2は多発しているかまたは中ないし低分化腺がんを言います。
病期B
腫瘍が前立腺内に限局しており、しかも転移のないものです。B1は片葉内に限局した単発の腫瘍、B2は両葉に浸潤しているものです。
病期C
がんが前立腺皮膜を越えて浸潤しているが転移を認めないものです。
病期D
転移を認めるもので、D1は所属リンパ節に転移の見られるもの、D2は大動脈分岐部リンパ節より上のリンパ節もしくは前立腺以外の臓器に転移を認めるものです。
治療
治療法は前立腺がんの悪性度、進行度や年齢、全身状態あるいは個々の患者さんの希望などによって異なりますので、主治医とよく相談することをおすすめします。主な治療法について簡単に説明します。
無治療経過観察
80歳以上の高齢の患者さん、がんの悪性度が高くない場合、がんの大きさが小さいなどの場合、治療せずに経過観察をすることもあります。
ホルモン治療
ほとんどの前立腺がんはその発育が男性ホルモンによって促されるため、この男性ホルモンを抑えるという治療法です。手術によって両側の精巣(男性ホルモンを分泌する)を摘出する方法と、注射で精巣からの男性ホルモンの分泌を抑える方法があります。また抗男性ホルモン剤を使用することもあり、どういった方法が良いかは個々の患者さんによって異なるため主治医と相談することが大切です。
手術療法(前立腺全摘術)
通常、ホルモン療法でがんを根治することは難しいので、患者さんの年齢やがんの進行度、全身状態などによってはがんそのものを手術によって取り去ることも考えます。前立腺を摘出したのちに膀胱と尿道をつなぎ直すという方法です。手術のリスクもありますのでその適応には総合的な判断と主治医との十分な相談が必要です。
放射線治療
体の外から放射線をあてる方法(外照射)と、体の内部からあてる方法(腔内照射)があります。腔内照射にはさまざまな制約があるため、現在我が国で施行している施設はまだ少ないのが現状です。こちらも主治医とよく相談して考える必要があります。 以上、代表的な治療法について解説しましたが、これですべてではありません。治療法を決めるにあたっては、やはり主治医と十分に相談することをおすすめいたします。
